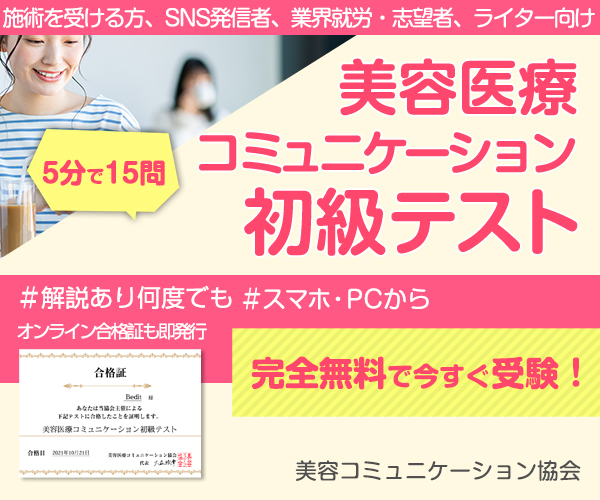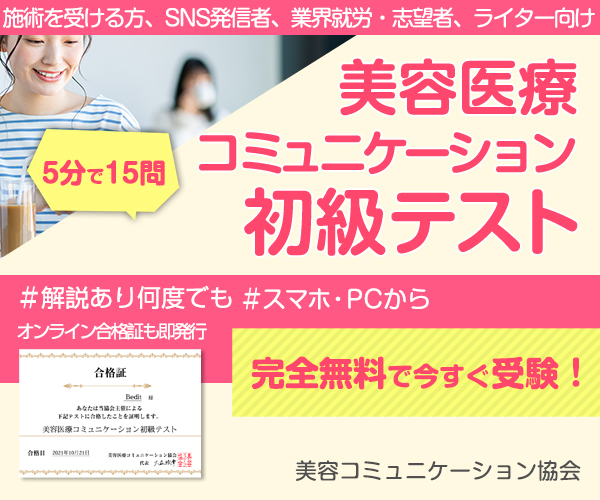
落語、面白そうかも・・・見てみたい!
皆様、落語はお好きだろうか。また、興味はおありだろうか。筆者は「日本人に生まれたし、いつかは日本文化を楽しめたらいいなあ」と漠然とした気持ちだけはあったものの、特定の分野への興味はなく、知識もゼロ。しかし、落語の漫画がきっかけで興味を持ち、行動に出ることにした。
落語をテーマにした漫画にハマる
漫画『昭和元禄落語心中』にハマった。どのくらいハマったかというと、続きが気になって仕方がなくなり、閉店直前の書店へ走り、間に合わなかったが諦めきれず、次に某レンタルショップへ走り、その場にあるだけ借りたくらいだ。
大衆文化として誰でも受け入れる気安さと、師弟関係を繋いで何百年と続いてきた伝統の重み。ネタというひとつの枠を丁寧に受け継ぐ中で、噺家の一人ひとりが自身の個性(話し方)を育てて磨く。相反するはずの要素が共存している落語が不思議なものに思え、惹きつけられていた。
都内で毎日やっているだと!?寄席を知る
やっぱり生の落語を聞いてみたくなる。落語は寄席という場所で聞ける。なんと年中無休、毎日開場しているという。現在、都内で寄席があるのは新宿、池袋、浅草、上野など。仕事や遊びではもちろん、乗換え駅としてもよく利用される場所にある。
開場時間は、場所にもよるが、正午前後から夜九時ごろまで。入場と退場は自由にでき、予約もいらない。つまり、気が向いたときにいつでも、ふらっと立ち寄ることができるのだ。
女性一人、新宿の寄席に突入!
「それなら今行こう!」と、我慢できずに自宅を飛び出した。知識は漫画で仕入れた程度で、しかも20代女性、極めつきに一人、浮くであろうこと必至だと筆者は思っていた。しかし、大衆文化の器、寄席の懐は広かった。
新宿駅の地下出口から徒歩2分で到着
着いた瞬間、「タイムスリップしてもうた・・・」とまず思った。やってきたのは新宿にある寄席、末廣亭(すえひろてい)。外観からすでに江戸の空気を漂わせている。周囲にはおいしそうな飲み屋が軒を連ねており、こちらもなかなかレトロな造りが多く、雰囲気がある。
券の代金は一般が3,000円。これ一枚で何時間でも楽しめる。シニアや学生、また会員、小学生だと安くなるようだ。着物割引という割引を設けているところもあるらしい。
ちなみに、寄席で支払う料金は木戸銭(きどせん)と呼ばれる。このことを初めて知った筆者は、江戸を感じさせる言葉の響きにときめいてしまった。外観と言葉に影響を受け、券を買うにも、「あ、一般一枚お願いします」ではなく、「よう、一般一枚頼むよ」と声をかけたくなってしまう。

意外に若い人もいる!解説もわかりやすい
入場してすぐ、映画館のような座席と、その両脇にある畳席があった。どちらも多いのは、やっぱり年上の方々の姿。しかし、ぐるっと見渡すと、ちらほらと同年代と思われる人たちや親子連れの姿が見える。若い世代は少数派ながらも決して珍しくはないようだ。
江戸の言葉もよくわからず、どこまでついていけるかと思いきや、噺の中にさりげなく解説が入る。たとえばわかりづらい言葉を○○、現代語訳を●●とするなら、噺の登場人物たちの会話で、
「○○を売って来い」
「え、○○って●●のことですか?」
というように、聞く中で自然と理解ができるように解説が入る。また、ネタ自体も古典的な噺だけでなく、時事的なことや個人的なことをネタとして話す噺家もいた。もちろんネタや噺家の考えによって同じとは限らないが、この日、数時間落語を聞く中で、理解に困ったことはなかった。
落語だけじゃなかった!奇術ありコントあり!
落語だけを楽しむのかと思いきや、出演者の一覧には奇術やコント、漫才、太神楽まであった。落語とは笑いの種類が違ったり、そもそも笑いを狙いとしていないものもある。落語とは違う演目があると、場があらためて新鮮な空気に変わったようになる。着物を締める帯のような効果もあるのかもしれない。

トイレどこ?畳席ってどう振舞う?
お中入り(休憩)が入り、トイレを探す。すると、清掃に動いていたスタッフと目が合った。
「あの、女性用のトイレってどっちでしょう?」
「(すっと指して)あっちです。奥のほう、右側です」
「ありがとうございます」
トイレから戻り、今度は畳席に移ってみる。先ほど畳席に座る人を見ていた筆者は訳知り顔をして、脇にある使用自由な座布団を取って座った。すると、スタッフが私のスニーカーを持ってやってきた。そして、私の座っている畳席の目の前にある、台型の柵の蓋をぱかりと開けて、
「失礼します。ここに入れておきますね」
「あ、ありがとうございます」
スタッフ様の素晴らしい気配りに、お中入りの始終お世話になりっぱなしだった。
ちなみに、寄席は飲食自由だ。売店にはお弁当やお菓子も売っている。筆者は小腹が空いたため、途中でお菓子を購入した。落語を聞きながら、甘いものをもしゃもしゃ食べるのは、少し贅沢な心地がした。
笑わせる噺家+笑いにきた客
「噺家にいじってほしいなら、最前列へどうぞ」と聞いていたが、本当だった。入退場などで動きを見せたときはもちろん、座っているだけでもいじられる。ちなみに、出演者同士や有名な噺家のこともいじる。日本人のツンデレは、どうやら江戸時代からすでにあったと見た。
落語は、思っていた以上に笑ってしまった。時代云々は関係なく、噺の登場人物たちの「人間臭さ」がおかしくてたまらない。そして噺自体の面白さに加えて、噺家は笑わせようとするし、客は笑いたいし、笑い声に包まれることでさらに笑ってしまうので、それがなんでも笑えてしまう空気につながっているのかもしれない。一人で、テレビを通して観ていたら、とても味わえない温かな空気だった。
退場して新宿の街並みを見て、ふっと目を覚ましたような気持ちになる。時代がかった外観と内装、そして噺家の言葉にすっかり酔っていたのだと気付いた。寄席は昼の部、夜の部に分かれているが、新宿は入れ替え制ではなかった。今回は思い立って行ったため途中からの入場になったが、次はお弁当を購入して、一日いてみたいと思う。

いつでも気軽に行ける寄席
入退場自由、席自由、飲食自由、笑い声歓迎と、寄席のルールはかなり自由度が高く、長時間でもリラックスして聞くことができる。また柔軟にネタを変化させている噺家が多く、江戸の言葉に明るくない筆者も理解に困らなかった。
そして思いのほか、人と一緒に笑うというのは温かく気持ちがいいと知った。江戸時代からそうだったように、「ちょっと興味があって」「なんか面白そう」などと軽い気持ちで、ふらりと立ち寄るくらいでいいのかもしれない。