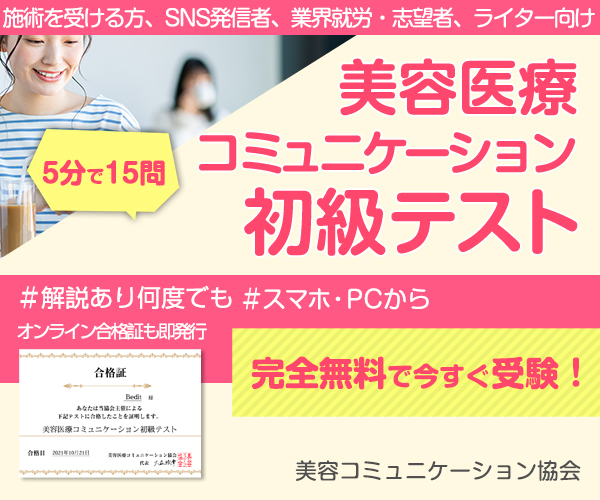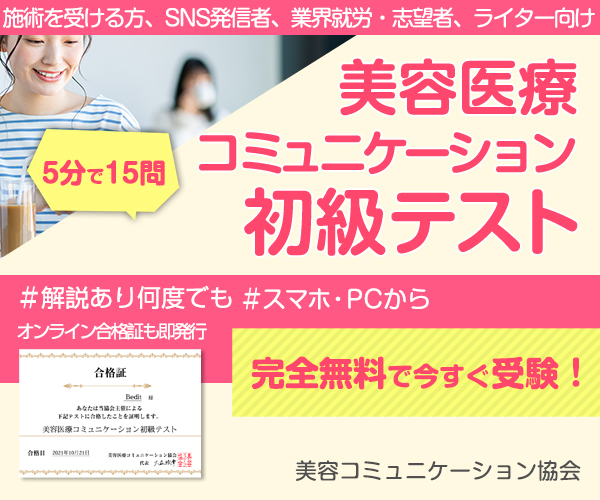
糀?麹?どっちが正しい?
「飲む点滴」と言われる甘酒。最近は夏もよく見かけるようになりました。というのも、疲労回復効果が高く、食生活が乱れがちな夏にこそ効果があると言われているからなんです。この甘酒を筆頭に、日本人の生活に欠かせない味噌や醤油。これら発酵食品を作る元となる「こうじ」についてお話しします。

さて、「こうじ」という字を調べてみると、漢字には「糀」と「麹」という表記があります。意味的には「米や麦を蒸したものにこうじ菌をまぶしたもの」であることは同じようなのですが、漢字の成り立ちという意味で違いがあります。
「糀」のほうは「米に花が咲いたように生えるカビの様子」を表すのだそうです。米に花が咲く、ってなんだか素敵ですよね。ということで、以下においては「こうじ」の表記は「糀」で統一したいと思います。
糀の歴史
ではこの「糀」。日本人は一体いつからこの糀を使ってきたのでしょう。
糀の起源は紀元前の中国。人々は、糀を使って今でいう醤油や味噌、みりんのような調味料を作っていたといわれています。
弥生時代になると、日本に米を作る技術が伝わりました。このとき糀を作る技術も一緒に渡ってきたと考えられています。まさに、米と糀は「切っても切れない」関係だったのです。古墳時代になると、米と糀を使った日本酒の元祖のようなお酒を造っていたという説もあります。
さらに時は流れ、奈良時代になると文献に糀のことが登場するようになります。『播磨国風土記』という書物に「乾飯がぬれてカビが生え、これで酒を造った」という記録が残っています。
その後、室町時代になると、糀のカビの胞子だけを集めて使いやすくした「もやし」と呼ばれる商品が販売され、より糀が人々にとって身近なものになりました。

そして、江戸時代になると、「甘酒」が登場します。夏の暑さを乗り切る知恵として、甘酒を飲むことが庶民の間で広まっていったのです。このことから、「甘酒」は夏の季語となっています。
このような経緯を経て、糀は日本人の生活に根付き、食文化を含めた日本文化を形成していく一要因となっていったのです。
世界から注目される糀を使った日本の食品
ところで、今、世界で日本の発酵食品が注目されていることはご存知ですか?
たとえば醤油

今、日本でもお馴染みになったグルメガイド『ミシュラン』に掲載されるほど有名どころのレストランのシェフたちがこぞって注目しているといいます。中、「ヌーベル・キュイジーヌ」と呼ばれる新しい傾向のフランス料理のスターシェフ、アラン・デュカス氏は、自分でプロデュースした日本酒を出すほどの日本びいきですが、彼は「うまみ」を引き出すために、好んで醤油を使っているといいます。
そして味噌

味噌においては、「放射線による消化管障害に味噌が効く」という研究結果が発表されたことにより、チェルノブイリ原発事故で被害を受けた主な被災地域(ロシア、ウクライナ、ベラルーシ)の食卓にこぞって取り入れられるようになりました。
日本の糀ブームはまだまだ続く!
数年前、「塩糀」を使った料理が流行ったのは記憶にも新しいところです。肉に漬け込むだけで、柔らかくして、しかも栄養価を高めて味も良くなると大ブームになりました。今でも、料理に「ちょい足し」するだけでおいしくなると、重宝している人も多いようです。糀は、もはや一過性のブームから定番へと定着した注目の調味料になったといえるでしょう。


糀を使った食品は、現在たくさん発売されています。甘酒の発祥の地とも言われる宮崎で、牛乳を専門として販売してきた私たちが、牛乳で造った甘酒ドリンクを開発することになったのは、もはや天命であったと言っても過言ではないでしょう。
開発のきっかけは、口蹄疫の被害に悩む酪農家さんの振興のためでしたが、いざ作ってみると、通常の甘酒よりも、牛乳よりも栄養価が高く、体を形作るために必要な必須アミノ酸を非常に効率よく吸収できることが分かりました。自然な甘さとほのかな糀の香り。機会があれば是非飲んでいただければと思います。
私たち日本人が古来から親しんできた糀。これからも日常生活にうまみく取り入れて、体の中から美しく健康になりたいものですね。