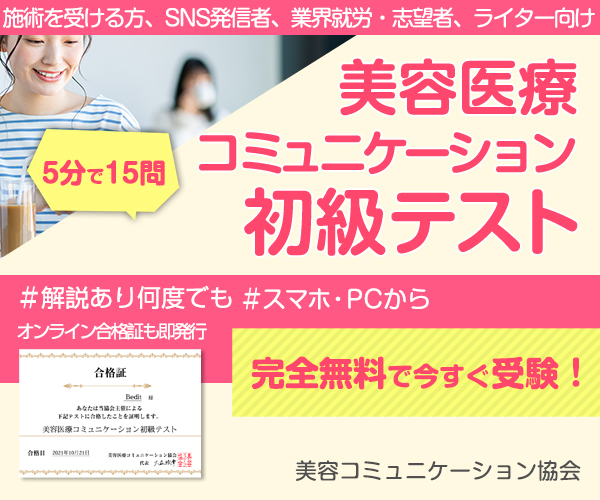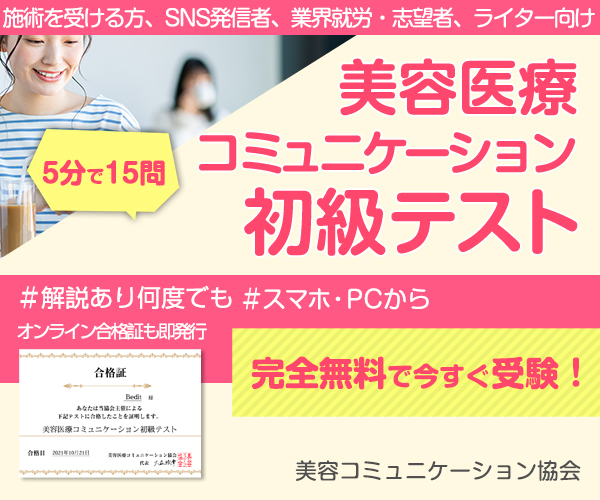
人は有機物、野菜は無機物が栄養
そもそも、野菜にとっての「栄養」とはどのようなもののことをいうのでしょうか。私たち人間は生物由来の「有機物」を口から取り込んで栄養としていますが、植物は「無機物」を直接吸収して育ちます。
「無機物」とは、地球が誕生したときから存在する物質のことで、窒素、リン酸、カリウムなどのこと。市販の肥料はこの「無機物」を野菜に与えることを目的に売られています。と、ここまで読んで、「え?でもお店には有機肥料が売っているよ」と思われたかたもおられるのではないでしょうか。今回はこのあたりの疑問をスッキリさせたいと思います。

有機物の肥料とは
先ほど、野菜の栄養は「無機物」とお伝えしましたが、その「無機物」は有機物が土壌の微生物によって分解されることで無機物の形となります。“有機”と名のつくものはこのしくみを利用した肥料です。
一方、窒素やリン酸、カリウムなどの「無機物」がそのまま入っているのが化学肥料です。化学肥料は有機肥料のように分解の過程を経ないので、与えれば基本的にはすぐに施肥の効果を発揮します。ただ、化学肥料の中にも栄養分を樹脂で覆ってゆっくり効かせる工夫をしているものなどがあり、一概に「化学肥料だから即効性がある」とはいえません。
効き目だけで選ぶと失敗する!?肥料選びの本当のポイント
有機肥料と化学肥料、結局のところどちらがいいの?と迷ってしまうのが菜園ビギナーさんだと思いますが、肥料は効き目の早さや効果の内容以外に、選ぶうえでの大切なポイントがあります。それは“土の生態系”です。
有機肥料は、土に住む微生物の活動を利用して必要な栄養素を野菜に与えます。このしくみは土の生態系に反することがないので、野菜にとってのより自然な環境づくりに貢献します。一方、化学肥料は野菜に必要な栄養分をダイレクトに届けることのみを目的としていますので、与えすぎるなど使い方を間違えると土の力を弱め、実がつきにくくなる、病害虫に弱くなるなどの弊害が起こる危険があります。

肥料は有機中心、化学はピンポイントで
こうしたことを踏まえると、肥料の与えかたは、「有機を中心にし、化学はピンポイントで」という形が理想です。具体的には、
- 苗の植えつけの際に施す元肥(もとごえ)には有機肥料を使い、その肥料の効果が現れるまでは化学肥料を施す。
- 野菜が実をつけたら追肥(おいごえ)として化学肥料を与える。
などです。“有機肥料で土を生かしながら、生育過程で足りなくなる栄養を化学肥料で補う”、のイメージです。

野菜に必要な栄養素はコレ!おさえておきたい基本
これまで、有機肥料と化学肥料の違いや使い方のイメージをお伝えしましたが、有機肥料も化学肥料も、「無機物を野菜に与える」という目的は同じです。市販されている肥料にも、その栄養素が数値として示してあります。以下は野菜に必要な栄養素の基本です。
三大要素
野菜にとって最も大切な栄養素です。
- 窒素(N):葉肥えといわれ、葉や茎の生育に必要な栄養素です
- リン酸(P):実肥えといわれ、花や実の生育を促します
- カリウム(K)根肥えといわれ、根の発育を促進します
中量要素
三大要素の次に大切な栄養素です。
カルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)、イオウ(S)
微量要素
わずかな量ですが必要です。
マンガン(Mg)、ホウ素(B)、鉄(Fe)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、モリブデン(Mo)、塩素(Cl)

有機肥料も化学肥料も、与えすぎは害
では最後に、肥料を与える際の盲点であり、同時に最も大切なことをお伝えします。ここまで読んで、「そうか、有機肥料は自然由来で安全だから、化学肥料とは違って多少やりすぎてしまっても大丈夫なのね」と思ったかたもおられるのではないでしょうか。
確かに有機肥料は自然由来のものを原料としており、土の生態系によってその効果をもとめることから比較的安全なものではあるのですが、化学肥料と同じく、与えすぎには注意が必要です。有機肥料は、高温時にはより活発に働く微生物によって多くの栄養素を土に与えますが、反対に低温時には溶け出す栄養素も少なくなります。
それならば、ということで低温時に有機肥料を多く与えてしまうと、分解されずに残ってしまった有機肥料が高温時に大量に分解され、栄養分が過剰になってしまうのです。化学肥料は与えすぎても水で流してしまえばある程度被害は回避できますが、有機肥料は水に溶けませんので、一度に必要以上の量を施してしまうと、対処のしようがなくなってしまうのです。
以上のことから、肥料は、適量の有機肥料を基本とし、必要にあわせてピンポイントで化学肥料を施す、というスタンスを保ちましょう。
出典:
「育つ土」を作る 家庭菜園の科学 木嶋利男
おいしいベランダ野菜 小島理恵
菜園生活パーフェクトブック 藤岡成介
ベランダ菜園スタートBOOK 平野編集制作事務所