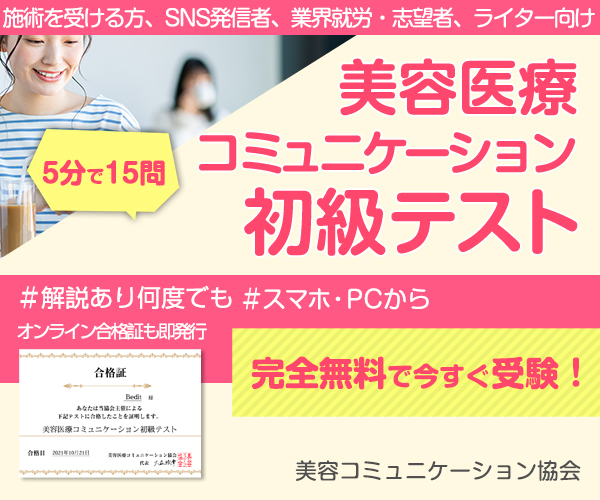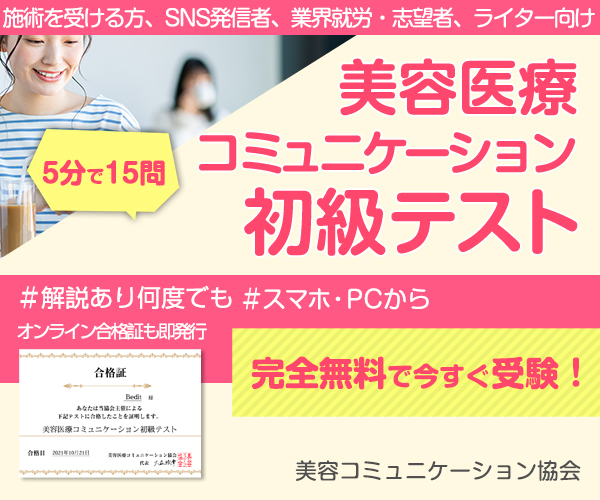
1.目標を決める
本を出すのが夢、という人ならば、出版翻訳を。
映画の字幕や海外ドラマを訳せるようになりたい、と考えているのなら、字幕・映像翻訳を。
とにかく翻訳を仕事にしたい、と考えているのなら、技術・実務翻訳を。
この分野には、IT、医療、金融、法律、特許など、さまざまなジャンルがありますので、少しでも知識のある分野を選ぶと、勉強もしやすいと思います。
翻訳には、大きく分けて、出版、字幕、産業という3つの分野があり、それに応じて勉強のやり方も変わってきます。
自分が何をやりたいのか、どのくらい時間とお金がかけられるか、よく考えてみてください。
翻訳は自分の楽しみとして、できるだけお金をかけずにやっていきたい、という人以外は、できるだけ翻訳スクールや専門学校へ通った方が近道でしょう。
そうやってあるていど力がついたら、自分がプロとして通用するかどうか、トライアルを受けてみてください。
2.読む能力、書く能力を鍛える
どのような人が翻訳家に向いているのでしょうか。
プロの翻訳家が口を揃えていうのは、読むこと・書くことが好きであるということです。
外国語でびっしり書かれた膨大な量の文章を翻訳するのですから、読むことが苦にならない能力は、翻訳家に何よりも求められるものかもしれません。
まずひととおり、目を通し、さらに、一行、一行訳しながら、何度でも読み返していくのですから、「長い文章を読むのがめんどう」などと言っていては、できることではありません。
さらに、日本語として一読すれば意味が取れる文章を書ける能力は必須です。
読み返してみて、自分の訳文の論理関係がおかしいところは、まちがいなく誤訳ですから、それに気がつけるくらいの感度も必要。
日頃から、新聞や雑誌に目を通し、それを要約したり、感想をまとめたり。
日々のちょっとしたトレーニングが、目標に向かって走る基礎体力となります。
3.辞書を引いたり、調べたりする習慣をつける
常盤新平さんの自伝的小説『遠いアメリカ』の中に、戦後間もない日本で翻訳をしている主人公が「ハンバーグステーキ」が何かわからなくて、頭を悩ませる場面がありました。
確かに生活習慣がまるでちがっていれば、単純な言葉ひとつが、何をいったい指しているのかわからないことも起こってきます。
それを思えばいまの私たちは本当に恵まれています。
ネットで検索すれば、言葉の意味だけでなく、画像や動画まで出てきて、それがどんなものか一目瞭然なのですから。
ニュースで知らない国や、初めて知るような情報を目にしたら、すぐに調べる習慣をつけましょう。
また、電子辞書もありがたいもの。
中でも翻訳家を目指す人にとってありがたいのが、セイコーインスツル(SII)の電子辞書です。
「リーダーズ第3版」「リーダーズ2+プラス」「ランダムハウス」「ジーニアス」という4大英和辞典、さらには「オックスフォード英英辞典」だけでなく、文法書や国語辞典まで入った、文字通りのスーパー電子辞書。
(搭載辞書一覧:http://www.sii.co.jp/cp/products/english/dfx9000/contents.html)
とんでもない誤訳が起こってくるのも、知っていると思って、辞書で確かめずに訳した単語がそれとはちがう意味だったから、なんてことが実に多いのです。
辞書を引き、言葉の向こうに目をこらし、この語はどのような意味領域を背負った言葉なのか、まで日本語にすくいとってやらなければなりません。
4.好奇心のアンテナを張り巡らせる
得意分野を持つことは大切です。
でも、それと同じくらい大切なのが、いろんなことに興味を持つこと。
たとえロマンス小説であっても、情景描写を正確に訳そうと思ったら、家の構造の知識が必要になってくることもあります。
ここはいったいどういうふうになっているんだろう、と、原文を元に想像し、ネット検索したり資料に当たったりしながら、実物を調べ、それが日本の読者にパッと理解できるような、正確な日本語に移し替える。
そのためには、想像力、調査力、知識、表現力、さまざまな能力が求められます。
でも、それができるのも、「なんだろう」「どうしてだろう」「どうなっているんだろう」という好奇心があってこそ。
5.強い目的意識を持つ
プロの翻訳家になるには、さまざまな翻訳会社が実施しているトライアルを受けてみることが第一歩です。
産業翻訳であれば、トライアルに合格すれば、登録、仕事が紹介される、という流れになっています。
その他、日本翻訳連盟が実施している「ほんやく検定」などもあります。
ところがこのトライアルに合格するのが大変。
受けては落ち、を繰りかえすことになりますが、結果を謙虚に受け止め、チャレンジ精神を決して失うことなく、挑戦を続けることが大切です。
また、文芸翻訳の検定は、なかなか仕事に結びつくことはむずかしいですが、それでも自分の力が客観的に評価される機会です。
「文芸翻訳検定」や
「出版翻訳オーディション」を受けながら、実力アップを目指してはいかがでしょうか。
楽な道ではないけれど、好きなことだからがんばれる。
好きなことだから、続けられる。
“I don’t know what lies around the bend, but I’m going to believe that the best does.”
村岡花子さんは『赤毛のアン』のこの箇所を
「曲がり角を曲がったさきになにがあるのかは、わからないの。でも、きっといちばんよいものにちがいないと思うの」
と訳しました。
あなたならどう訳しますか?