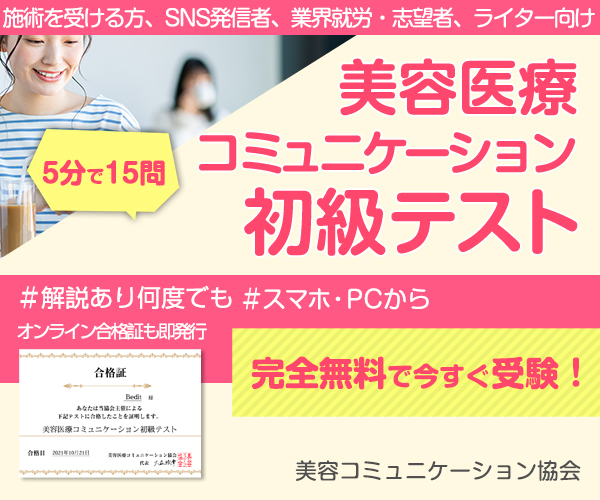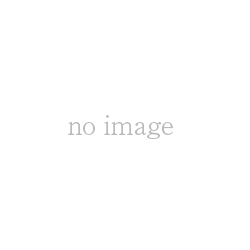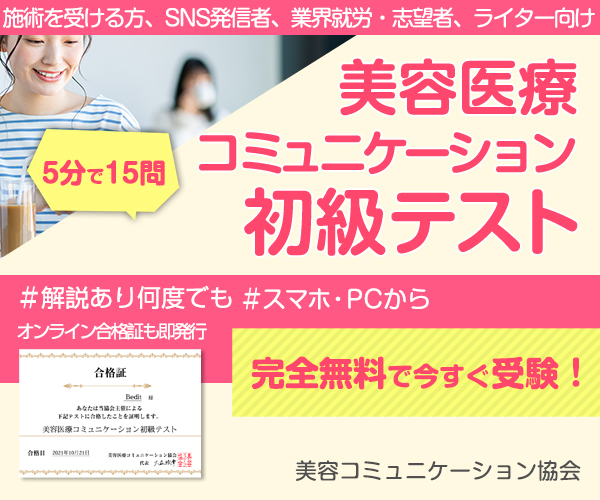
1. 廃棄型節約法とは
廃棄・廃止という行為の特性を考えます。
1.1 廃棄型節約法の性質
(1) 節約の手段の中でも強烈なのは、機能している事物・制度・慣行を廃棄し廃止する手法です。ある時まで機能していたものが消滅するのです。頻繁に使う手法ではありません。
好んで行うのではなく止むに止まれぬ事情から行うのです。躊躇なく断行できるとすれば、もっと以前に断行すべき廃棄を怠っていた場合でしょう。
(2) 廃棄される対象に関わる個人・団体・組織は当然反対します。生活基盤を失う可能性があるほか、これ迄の努力や献身が否定されているようだからです。
明治維新の際に断行された版籍奉還や廃刀令は武士階級に厳しいものでした。バブル崩壊のあおりを受けた北海道拓殖銀行や山一證券の廃業などは、節約とはやや異なるものの、それ迄活動していた名門企業の消滅です。関係者に深刻な影響を与えます。
1.2 廃棄型節約法の目的
断行する当事者の状態には以下の場合が考えられます。状態Dは追い詰められていますが、緊迫してはいても状態Cは事業継続の意思があります。廃棄型節約法は事業継続の手段に行うことを忘れてはなりません。
- 状態A: 存続の危機は全くないが、当該事物は明らかに不要なので廃棄する。
- 状態B: 存続の危機は感じないが、候補物件を廃棄して経営に有効に使いたい。
- 状態C: 危機の渦中にあり、事態の改善のため当該事物を廃棄せざるを得ない。
- 状態D: 廃業の過程で当該事物を廃棄する。
2. 廃棄・廃止が必要な要因
廃棄・廃業・廃絶は苦渋を伴うため採りたくない選択肢です。しかしそれに至る原因は様々で誰もが必要になる可能性があります。
2.1. 外的要因
社会情勢の変化や事件の影響を受けます。下記はその例です。
- リーマンショックやサブプライムローン
- 米国のドル放出による劇的な円高変動とその長期化
- ギリシャやスペインなどの信用不安
- 中東の政治的不安と戦争勃発の危機
- 世界経済の構造的変化
- 競争者の出現 例えば競合店の進出
- デフレ経済が続く日本経済
- グローバル化による中間所得層の崩壊など
2.2 内的要因
自らが発生させた要因です。例を以下に示します。
- 新製品開発の失敗による売上低下
- 拡大政策の失敗
- 多額の債務による金利負担の増大
- 不適切な経営による利用者減や売り上げ不振など
3. 廃棄・廃止対象の検討
企業、政府自治体、学校法人、家庭、個人のそれぞれの立場から、廃棄・廃止を選択する基本的な考え方を示し、代表的な例を挙げます。また、設計者が考えるべき着眼点も挙げます。事業継続を前提とすれば、廃止対象に事業の主体、収益の柱を含めないことは当然です。
3.1 企業の場合
企業では下記の事物・制度が対象として考えられます。
(1) 事業関連
今後の見通しから事業規模の妥当性を見直します。下記の項目はその例です。
- 事業の売却: 土地・建物・設備・従業員などの売却先への譲渡
- 不採算事業の廃止: 不要になる土地・建物・設備の売却・廃棄
- 事業の縮小: 不要になる土地・建物・設備の売却・廃棄
- 事業部門の子会社化: 子会社の売却、子会社の他企業との合併など。
(2) 資産関係
有形・無形の資産の維持費や活用の度合いを見直します。例を示します。
- 施設・設備の売却または廃棄
- 寮・社宅の廃止
- 機械・設備の廃止・売却
(3) 人材関係
事業単位の見直しだけでなく、全社的視点から人材・人員を見直します。必要なら希望退職者を募りますが事業の発展に必要な社員の退職は避けねばなりません。
(4) 広告宣伝関係
インターネットの活用を含めた新たな視点で広告政策を見直さねばなりません。なお、運動部の存廃は社会貢献の意味からも慎重に扱うべきです。運動部もまた自営の信念をもつべきです。
(5)制度・慣行
これまでの制度や慣行を廃止の観点で見直します。下の項目はその例です。
- 出張関係: グリーン車の利用禁止、ビジネスクラスの利用禁止など。
- 通勤手当関係: 上限を設けるなど。
(6) 経費関係
廃止・削除の視点から光熱水費、通信費などの経費を見直します。
(7) コンピュータ関係
サーバーコンピュータの能力向上やクラウドコンピュータの利用技術が進歩しています。廃止・廃棄の観点からもコンピュータの利用政策の見直しが必要です。
3.2 設計者の場合
機器・設備・システムの設計者が行う設計の見直しです。置換型節約の候補に比べ数は少ないでしょう。開発時には必要だった過剰な機能・過剰な性能にはメスを入れる必要があります。
3.3 政府・地方自治体の場合
最近の新聞報道では、政府の長寿命化基本計画案によると不要インフラは廃止し、撤去費などは地方債などで賄うことを容認するようです。
作る一方だと批判された政府や自治体のインフラ政策もようやく変わるようです。
(1) 事業・サービス
実働してないものも含め、存在する事業・サービスを廃止・廃棄の視点で見直します。民間への移転も視野に入れるべきです。
- 事業・サービスの停止: 利用者が少ない事業・サービスを停止します。
- 廃止したサービスの施設や設備の処分・売却:
- 利用されなくなった道路・橋・施設などの撤廃:
(2) 人材
公務員の定員削減の立場から見直します。業務の内容や方法を含めて見直すべきです。
(3) 諸制度・慣行
廃止・廃棄の視点から制度・慣行を見直します。民間との釣り合いを含め、時代に合わない諸手当や天下りの制度はもちろん、官官接待や非常識に低い住宅費負担も廃止の対象にすべきでしょう。
(4) 経費関係
廃止・廃棄の視点から制度・慣行を見直します。
3.4 学校法人の場合
学校法人は、校舎、体育館、運動場、水泳プールなどの施設と教職員という人的資産で事業を展開します。廃棄型節約法の対象は限られます。
- 廃校: 廃業を意味する最後の手段です。継続の場合はあり得ません。
- 配下の学校の廃止: 大学が付属高校や付属中学を廃止する場合です。
- 土地建物の売却: 事業に必須でない有形資産の売却です。
- 知財の売却: 特許・著作権の売却です。
- 校外施設売却: 研修所・演習施設などの売却です。
3.5 個人事業者の場合
個人での事業は、食堂、理髪、八百屋、魚屋、写真屋、不動産屋など業種は様々です。
極端に経営が悪化しない限り、廃棄・廃止の機会は少ないように思います。下記の項目は事業が悪化した場合の廃棄の例です。
- 個人資産の売却: 土地建物 ・会員権・有価証券など
- 各種保険の解約
- 高利負債の一括返済
3.6 家庭の場合
家庭は家族の生活の場であり、子育ての場であり、心身を休め、明日への活力を養う場であり、人格形成の場です。
それらの活動に必要な事物の廃棄・廃止は、失業や長期の病気など危急の場合を除きあり得ません。
なお、乳母車やチャイルドシートのように、時の流れの中で不要になる事物はあります。
(1) 自然の成り行き ・不要になった物品の売却や廃棄
(2) 家計の危機の場合
- 固定電話の解約、朝刊の購読廃止
- 塾・家庭教師・教材などの解約
- 各種保険の解約
- 高校・大学などの退学
3.7 個人の場合
各人はその人固有の世界を作りつつ、勤労と趣味その他の活動で社会とかかわっています。個人の責任で、何を残し、何を得、何を廃棄するか考えねばなりません。自己責任に耐えられない子供は大人の指導が必要です。下記の項目は例です。
- 卒業、結婚、新築など様々な理由から不要になった物品を売却し廃棄します。自動車、バイク、電子機器などはその例です。
- 生命保険の解約はあり得ます。
- 各種の会員から脱会します。ゴルフ場会員、スポーツクラブなどです。
4. まとめ
廃棄型節約法の基礎的な理論を説明しました。現行の事物や制度を廃棄し廃止します。人や組織の大きな変化点に対応して行います。適用頻度は少ないものの、積極的な経営活動には不可欠の手法です。突発的に危機が発生した場合を除き計画的に進められるはずです。廃棄したものは戻って来ませんので慎重に行うべきです。