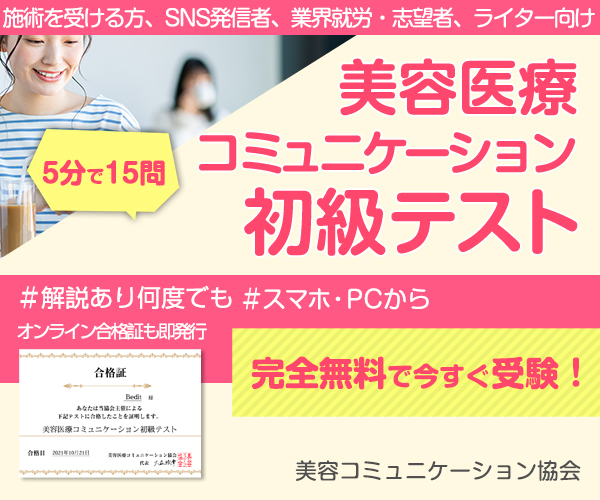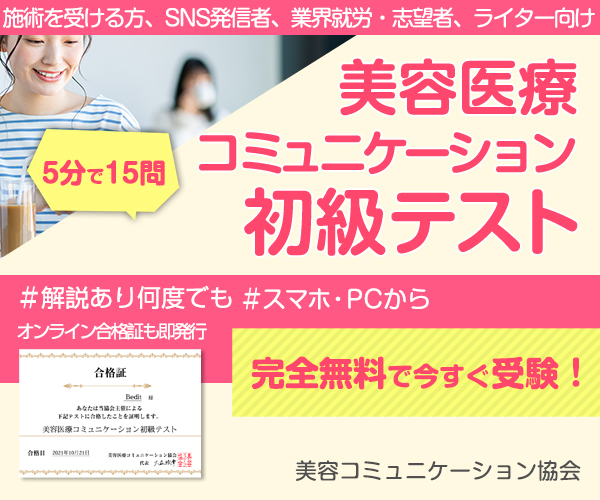
バランスが大切なサイズやカラー展開
展示会前のオーダーシートを作っている際に、決めなければならない重要なことと言えば、サイズやカラーの展開です。
たくさんのカラーがあれば魅力的に映りますが、生産する側としては手間もかかり大変になります。
バイヤー側も、カラーがたくさんあり過ぎると選ぶことができなくなり、結局サンプルと同じカラーの発注をする場合もあります。
これはサイズも同様で、適度な展開数に絞ることが発注を集めるブランド側の重要な仕事です。
そこで、サイズやカラーの絞り方や対応の仕方などをチェックしてみましょう。
ある適度、展示会を重ねると自身のブランドの評判が高いカラーやサイズの偏りが分かるようになります。

カラーの展開は少なめがベスト
カラーの展開はとにかく少なめを意識しましょう。
多くても3色展開、少なければ1色展開でも問題ありません。
特に始めたばかりのブランドであれば、カラー展開することで負担がかかることが多いです。
3色展開をするのであれば、発注が来た時のために生地を確保する際に3カラー分手配が必要になります。
特に卸売りの場合は、一反ごとに購入しなければ安くならないため、3カラー分の生地を用意することは大変です。
さらに、生地によっては手に入らなくなり、代替えの生地で対応せざる得ないこともあるので、トラブルのリスクも高まります。
ブランドを始めた最初のうちは、負担が少ない1色のみの展開など、自分が対応できる範囲での取り扱いに徹しましょう。
また、カラーの展開を増やすと、発注がバラけてしますことも負担になります。
縫製工場にとっては、カラーが変わることで、たくさんのミシンの糸を変えるなど、生産ラインの変更で手間がかかってしまいます。
それが原因で、生産コストが高くなることや納期が大幅に遅れるなどの問題が起こることがあります。
カラー展開を行う際は、しっかりと生産を行ってもらう工場と打ち合わせをしましょう。
サイズの展開はアイテムとターゲットのバランス
サイズの展開もカラーと同様で、少ない方が手間も負担も少なくなります。
アクセサリーやバッグなどはフリーサイズのみで問題ありませんが、ウェアにとってはサイズ展開が必要になってきます。
一般的なサイズ展開であれば、S、M、Lの3サイズにすることが多いです。
これによって、ある程度の広範囲の方をカバーすることが可能です。
ただ、もしブランドとして、小柄な方に着てもらいたい、小柄な方に似合うウェアをデザインしているのであれば、S、Mの2サイズに絞ったサイズ展開でも問題ありません。
仮に大きいサイズの要望があれば、その後のシーズンで対応することでも十分です。
さらに、シャツなどではなく、ゆったりと着られるポンチョなどのトップスであれば、フリーサイズでも対応できます。
アイテムによって展開するサイズを変えることで、できる限り発注がバラけないように工夫をしましょう。
またメンズブランドであれば、大きめサイズを充実させることも対策の一つです。値段の高価なブランドであれば、年配のお客さんの購入率が高くなることもあります。
そんな時には、Lサイズ以上を展開することで売り逃しを防ぐことにもなります。
さらに、ユニセックスに展開するのであれば、XS〜Lサイズまでと幅広くサイズを用意する必要もあります。
ユニセックスで着られるアイテムであっても、サイズの展開で生産に負担がかかるようであれば、最初はレディースのみの展開にするなど、サイズを絞ることも考えましょう。
サイズの展開だけでも、自分のブランドの特徴と照らし合わせて決める必要があります。
自分のブランドアイテムを買ってもらいたい方を思い浮かべながら、負担にならないサイズ展開を考えるようにしましょう。
生産をする際のコストも考慮することが大切
カラー展開とサイズ展開についてご説明してきましたが、生産する際に負担になるコストもしっかりと考慮しましょう。
仮に、ジャケットなら50着からでなければ生産をしてくれない工場であれば、展示会で56着の発注が着た場合、
1色展開であれば、56着で問題ないのですが。
2色展開であれば、Aカラー30着、Bカラー26着とバラつきがでることがあり、生産してもらないことや、生産コストが上がるケースもあります。
特に、小さいブランドであれば少ないオーダーをより一部のアイテムに集中させて発注を取れるかが、スムーズな生産のポイントとなります。
カラー展開を1色増やすだけで、オーダーの数がどれも少なく、生産してもらう工場との交渉などで不利な状況になることもあります。
サイズ展開に関しても、パターンを外部にお願いしているブランドであれば、サンプル以外のサイズ用のパターンを作ってもらう必要があります。
この違うサイズのパターンを作り直すことを「グレーディング」と言い、サイズに合わせて若干大きくや小さく作り直すことを指します。
もちろん、その作業値段は様々ですが、ジャケットやシャツなどのパーツの多いアイテムであれば、割高になるので注意が必要です。
もちろん、サンプルパターンをMサイズで作った場合、SサイズとLサイズの展開をするのであれば、2回分のグレーディング費用がかかります。
サイズ展開する際は、このグレーディング費用も考慮して上代を決めるようにしましょう。
イレギュラーは別注として対応可能
カラー展開やサイズ展開は、できる限り小さくすることで負担を少なくすることは分かりましたが、展開を小さくし過ぎることでの問題を考えてみましょう。
カラー展開を1色にした場合、バイヤーによっては他のカラーが欲しいと要望が出る場合があります。
サイズも同様に、顧客さんが大柄な方が多く、大きめのサイズを作って欲しいと希望されることもあります。
そんなイレギュラーな場合には、別注として提案してみましょう。
セレクトショップにとっては、ファッションブランドに対して自分達だけのオリジナルカラーやサイズを作ってもらえることはメリットになります。
話題性としても取り上げてもらえる機会も増えるので、お互いに得をする方法です。
その際に注意しておきたいことが、発注数です。
別注のカラーやサイズを作るとなると、生産のコストがかかることを忘れてはいけません。
そこで、コストがしっかりとカバーできるまとまった数量を発注してもらうように交渉しましょう。
その数が30点なのか、50点なのかは、工場との契約内容で違いますが、別注対応する代わりに、まとまった数の発注を取るようにします。
別注を行ったことがあるバイヤーであれば、生産状況などである程度の数量を発注しなければならないことは理解してくれます。
そのため、正直に生産の都合を説明すれば、対応してくれるバイヤーが多いです。
ただ、数量の問題やどうしてもこちら側に負担が大きい別注になりそうであれば、断るようにしましょう。
別注を行うのは、ブランド側もバイヤー側もメリットがある状態でなければ避けるべきです。
特に大手のセレクトショップであれば、店舗数も多く、買い付け予算も高いので、たくさんの数量の発注は問題ありません。
さらに、競合を差し置いて話題性を作れる別注は魅力的に映ります。
仮にバイヤーから、カラー展開に不満がありそうなら、別注の提案をしてみましょう。
思わぬ大きな発注に繋がることもあります。
自分が出来る規模で無理なく展開
サイズやカラーの展開は、たくさんあれば魅力的に映りますが、一番大切なことは、負担を少なくブランドを続けることです。自分ができる規模でバランスよく展開できるように、計画的に決めていきましょう。